最近入社してくれた技術スタッフ2名とBOスタッフ1名の成長が実感できる時期となってきました。
とてもとても、うれしいことです。
とくに技術スタッフの2人は、最初は現場で見る幻想的な炎がもの珍しく、ついつい見とれているだけの日々でした…。



当社は新入スタッフに対し、入社してから数年が一番仕事でキツイ時期であることを説明してます。
はじめのうちは先輩スタッフの指示のもと、連れていかれるだけ日々。
最初は緊張してがんばるけど、3か月くらい経つと会社に慣れてくる半面、仕事はあいかわらず「やらされている」だけなので、朝もつらくなってきて、だんだん心が折れてきて、そして、やめたくなる …。
その時期を先輩スタッフに励まされながら乗り越えられると、少しずつ仕事がこなせるようになり、自分の考えで自分のスケジュールが決められるようになってくると、仕事は徐々に「やらされている」から「自らやりにいく」ようになる。
「やらされる仕事」から「やりに行く仕事」に変わったときに、少しずつ仕事の楽しさとお客様や仲間への感謝の気持ちがわいてくる。



■ 「他人のため」のほうが力が発揮できるように人は作られているらしい…
極端な例になるが、たとえば今日から毎日腕立て伏せ&腹筋を100回ずつ3年間欠かさずにやるとする。
目的が筋力UPとダイエット (利己動機) である場合、一流のアスリート以外の一般的な人の多くは、飲み会や旅行など何かしらの生活イベントに当たったときに、それを言い訳にしてやらない日とする人が多い。 (利己動機からくる甘え)
でも、これを1日でも欠かせばあなたの家族や恋人に危害が生じる(利他動機)となった場合は、やり抜ける人が多くなるではないだろうか。
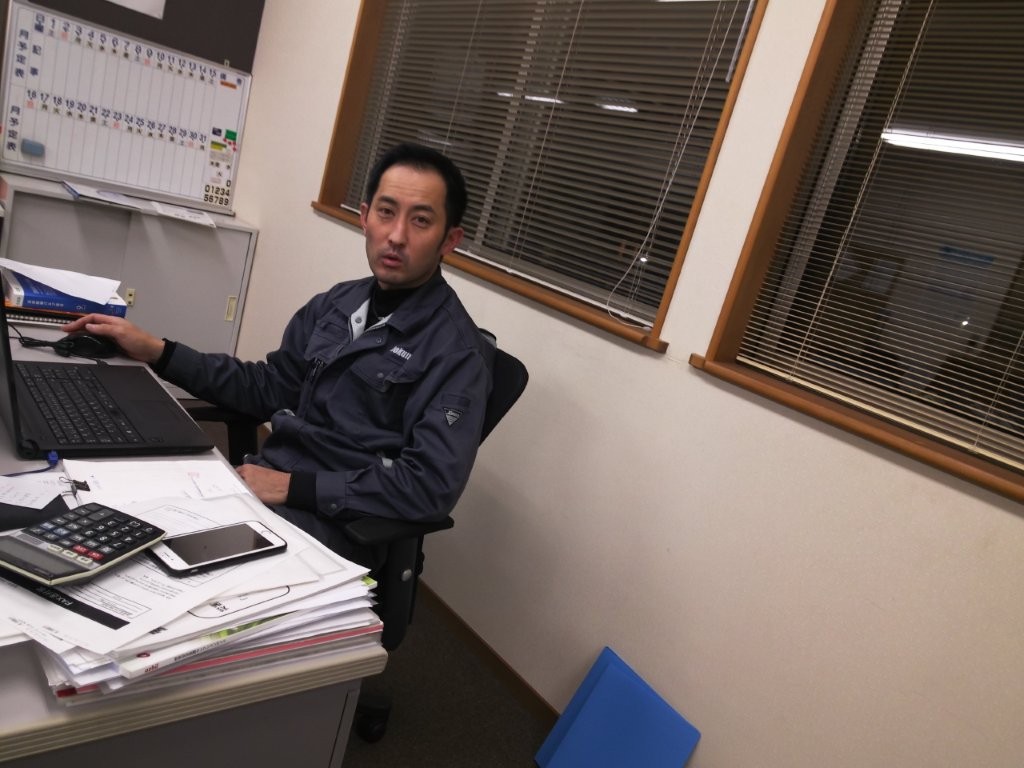

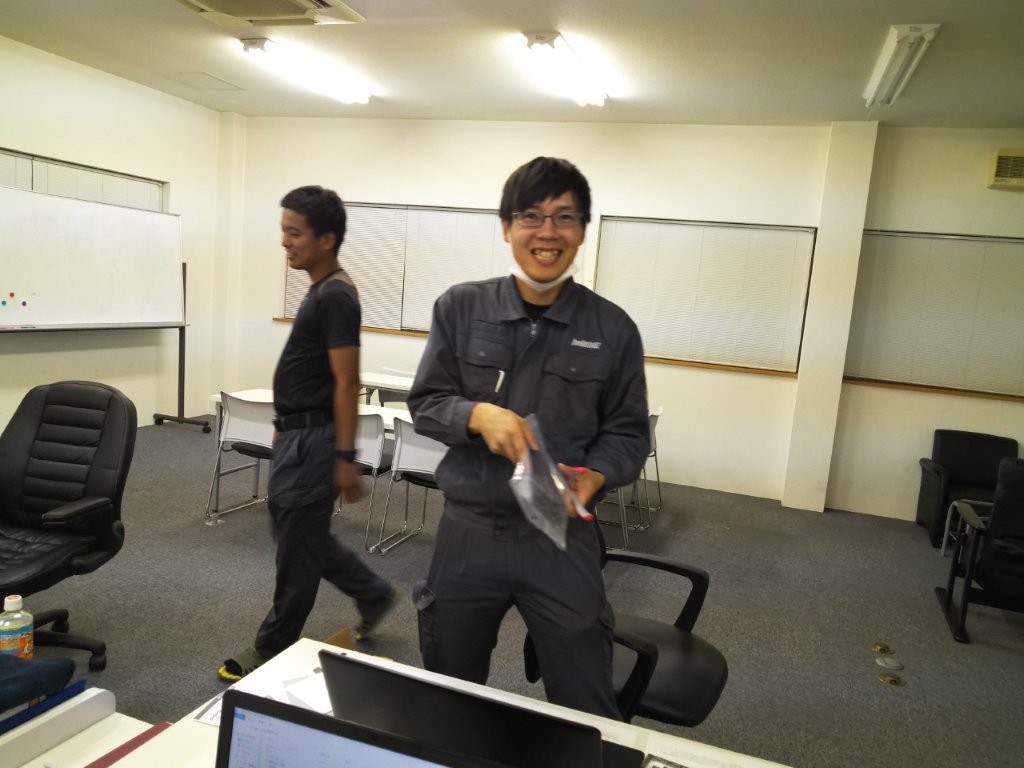
■ 社会貢献を主軸すれば「総どり」できる
人間が働く三大動機とは、
① お金を稼ぐため ※普遍的動機 / 仕事=「苦行」のまま終わる
② 自分の成長のため ※利己動機 / やる気はあるけど、甘えも生じる
③ 他人の役に立つため ※利他動機 (社会貢献) / 実力以上の力の発揮と継続力
★
②自己成長を目的として働くことは決して悪いことではない。
ただ、仕事の目的比率が「社会貢献<自己成長」になってしまっているひとは、仲間やお客様がお困りの場面でその本性が無意識に現れることがあり、そのときの言動や行動に違和感を感じられたとたん、徐々に距離を置かれ、チャンスを頂けなくなり、仕事の機会を失って、そのひとの成長はそこで止まる。
このあたりが、利己主義優位の考え方のひとの成長の限界点。
成長を遂げるためには、挑戦と失敗の改善の繰り返しが必要とよく言われるが、それ以前に他人からの支援がなければ、その機会すら与えられないということ。
社会や他人のために自己の力を使わない人・使えない人は、他人からのサポートに期待してはいけない。
③の心が芽生えてくると、お客様に喜んでいただけたことが自身の喜びに変えられるので、それがまた次の力となって新しいことに挑戦し、また実績がつき、社会的信用が増え、さらに他者からチャンスをいただき、またそれに成果が伴い、それを繰り返して繰り返したあとに、ふと気が付くと社会的地位が上がって、結果的に実入りが多くなり、仕事が「苦行」から「楽行」にかわり、最終的に①~③が総どりできる。
…かもしれない。



■ 利他主義へ思考を転換する方法とは
① 謙虚さ ② 感謝の心 ③ 自己利益を狙わない
人が不注意の失敗をするときのタイミングの多くは、慣れてきたときといわれる。
謙虚さを維持できれば、人間関係や技術習得の面で成長し続けられる。
感謝の心を忘れなければ、他人へのやさしさが育まれ、社会貢献の大切さが理解でき、他人から信頼される人格が形成され、結果的に人生が楽しく感じられるようになる。
③の自己利益を狙わないについては、「お金が欲しい」「地位と名誉が欲しい」「この仕事は金になる」などといった自己動機からスタートした事業や仕事の大半は自分が望む逆の方向に進んでしまうことが多いということ。
逆にうまくいっている事業や仕事の多くは、利他動機からスタートしたものといわれており、いろいろがっんばってきたら結果的に「地位」や「お金」が入ってきたという感覚。(ただ、その人にとってそれらが重要なことではないと感じる人が多い)
■ 最後に
人生の半分が仕事で費やされるのであれば、どうせなら楽しく感じられたほうがよいかなということで、当然例外も多くあるので一概にはこれが正解と言えないが、自分を凡人であるともし感じているのであれば、これもひとつの考え方として覚えておいていただければと思う。
仕事の価値をどう思うかは個人の自由であからして、これに共感ができなくとも、結局仕事は成果主義なので、自分の信じる価値。観、方法、モチベで成果を上げられればよいということ。
